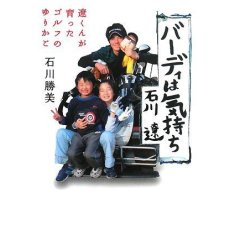2013年07月16日
円安VS円高
最近は経済関係の読書が多い、アベノミクスの影響か。次は百田尚樹さんの小説を読むつもりだ。さて今回の本のタイトルは「円安VS円高 どちらの道を選択すべきか」である。著者は円安主張の藤巻健史氏と円高主張の宿輪純一氏だ。どちらの意見もとても興味深い。
僕は藤巻氏の意見にやや軍配を上げたい。超円安は困るが少し前までの超円高は異常だと考えている。1$90円~1$110円のレンジが適正なレートではないだろうか。そういった意味では現在のレートは正常だと思う。超円高でどれほどの雇用が奪われたのか計算するだけでも恐ろしい。よくぞここまで(アベノミクス以前)放置してきたものだと思う。
藤巻氏によると円安になると日本の農業も世界で戦えるという意見は面白いなと思った。1$500円とか1000円とかになると現実的な数値ではないとは思うが1$150円くらいになってもおかしくはないのかも知れない。それほど日本の財政は深刻な状況にある。更に2015年から社会保障費の大幅な増加が見込まれている。そう団塊の世代が年金を受け取るからだ。
戦後、日本の経済は団塊の世代を中心に成長してきたのは間違いない。社会保障費問題もここを乗り越えると楽になるのだろうが険しい道のりだろうと思う。世代間格差を縮小しないといけない、政治は全ての世代に対して公平であるべきだ。
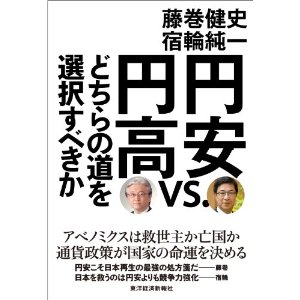
僕は藤巻氏の意見にやや軍配を上げたい。超円安は困るが少し前までの超円高は異常だと考えている。1$90円~1$110円のレンジが適正なレートではないだろうか。そういった意味では現在のレートは正常だと思う。超円高でどれほどの雇用が奪われたのか計算するだけでも恐ろしい。よくぞここまで(アベノミクス以前)放置してきたものだと思う。
藤巻氏によると円安になると日本の農業も世界で戦えるという意見は面白いなと思った。1$500円とか1000円とかになると現実的な数値ではないとは思うが1$150円くらいになってもおかしくはないのかも知れない。それほど日本の財政は深刻な状況にある。更に2015年から社会保障費の大幅な増加が見込まれている。そう団塊の世代が年金を受け取るからだ。
戦後、日本の経済は団塊の世代を中心に成長してきたのは間違いない。社会保障費問題もここを乗り越えると楽になるのだろうが険しい道のりだろうと思う。世代間格差を縮小しないといけない、政治は全ての世代に対して公平であるべきだ。
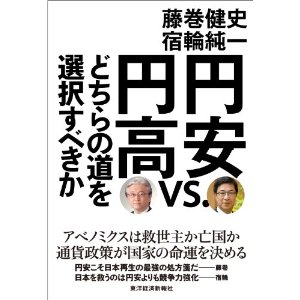
2013年07月08日
異次元緩和の先にあるとてつもない日本
著者の上念司(じょうねんつかさ)氏は前回のブログで紹介したイェール大学名誉教授・浜田宏一氏の教え子である。それだけに「アメリカは日本経済の復活を知っている(浜田宏一著)」とセットで読むと面白いかも知れない。
アベノミクスは始まったばかりでその成果が現れるのは半年から1年先であろう。アベノミクスで景気が良くなるという説とハイパーインフレやスタグフレーションが起こり景気が悪くなるという説がある。今後、企業業績が回復するか、雇用が改善するか注目していきたい。
個人的な見解であるが僕は景気が良くなると考えている。僕は経済学に詳しくはないが、この本の中の中に書かれている論理的な思考には納得できる部分が多いからだ。現にアメリカではリーマンショック以降の金融緩和で雇用が改善しているし株価も上昇している。株価が上昇しているということは企業業績が良くなっていると見て間違いない。追随する日本もアベノミクスによる景気浮揚を期待したい。
1991年以降の20年間を”失われた20年”と呼ぶらしい。あまりに長い20年だ、生まれた子供も成人している。ではこれからの日本はどうなるのであろうか。本当に自信を取り戻すことが出来るのであろうか。期待と不安が交錯する。

アベノミクスは始まったばかりでその成果が現れるのは半年から1年先であろう。アベノミクスで景気が良くなるという説とハイパーインフレやスタグフレーションが起こり景気が悪くなるという説がある。今後、企業業績が回復するか、雇用が改善するか注目していきたい。
個人的な見解であるが僕は景気が良くなると考えている。僕は経済学に詳しくはないが、この本の中の中に書かれている論理的な思考には納得できる部分が多いからだ。現にアメリカではリーマンショック以降の金融緩和で雇用が改善しているし株価も上昇している。株価が上昇しているということは企業業績が良くなっていると見て間違いない。追随する日本もアベノミクスによる景気浮揚を期待したい。
1991年以降の20年間を”失われた20年”と呼ぶらしい。あまりに長い20年だ、生まれた子供も成人している。ではこれからの日本はどうなるのであろうか。本当に自信を取り戻すことが出来るのであろうか。期待と不安が交錯する。

2013年07月07日
アメリカは日本経済の復活を知っている
イェール大学名誉教授、浜田宏一氏の著書である。最近この手の本を読むのが楽しい。現在行われている大胆な金融緩和、アベノミクスを支持する書物でもある。
僕は円高というのは日本の通貨の信用度が高くなって良いことだと思っていたが、さすがにここ数年の1ドル80円近辺の超円高は異常と考えていた。円高不況が産業の空洞化を招き、雇用とりわけ製造業の地方雇用を奪っている実情にこのままで日本は本当に大丈夫なのだろうかと不安に思っていた。円高の原因が日銀の金融政策にあると論破するこの本に対して異論を唱える方もかなりいるだろう。しかしながらここ数か月の為替の動向を見ていると明らかに円安になっている。金融政策が効いている証拠ではないだろうか。
通貨というのは高すぎても安すぎてもいけないと僕は考えている。適正なレートが必要だと思う。超円高で倒産した企業、失われた雇用はあまりにも多いのではないだろうか。また経済苦を理由にした自殺も後を絶たないし、生活保護世帯も増え続けている。円高デフレ不況による悪循環から早期の脱却が必要だ。そのためのアベノミクス、それが正しかったかどうかの判断はここしばらくの経済指標を見る必要があるが個人的には大いに期待している。
若者が夢と希望を抱く社会へと変わってほしい。そして新しいことにチャレンジする人たち、中でも起業を志す人たちが数多く出てきてほしい。僕も大したことはできないけれど起業家支援という新たな分野にチャレンジしていくつもりだ。
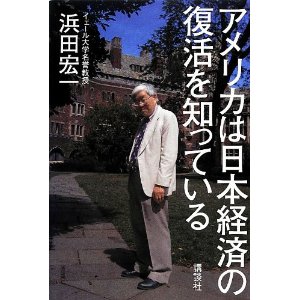
僕は円高というのは日本の通貨の信用度が高くなって良いことだと思っていたが、さすがにここ数年の1ドル80円近辺の超円高は異常と考えていた。円高不況が産業の空洞化を招き、雇用とりわけ製造業の地方雇用を奪っている実情にこのままで日本は本当に大丈夫なのだろうかと不安に思っていた。円高の原因が日銀の金融政策にあると論破するこの本に対して異論を唱える方もかなりいるだろう。しかしながらここ数か月の為替の動向を見ていると明らかに円安になっている。金融政策が効いている証拠ではないだろうか。
通貨というのは高すぎても安すぎてもいけないと僕は考えている。適正なレートが必要だと思う。超円高で倒産した企業、失われた雇用はあまりにも多いのではないだろうか。また経済苦を理由にした自殺も後を絶たないし、生活保護世帯も増え続けている。円高デフレ不況による悪循環から早期の脱却が必要だ。そのためのアベノミクス、それが正しかったかどうかの判断はここしばらくの経済指標を見る必要があるが個人的には大いに期待している。
若者が夢と希望を抱く社会へと変わってほしい。そして新しいことにチャレンジする人たち、中でも起業を志す人たちが数多く出てきてほしい。僕も大したことはできないけれど起業家支援という新たな分野にチャレンジしていくつもりだ。
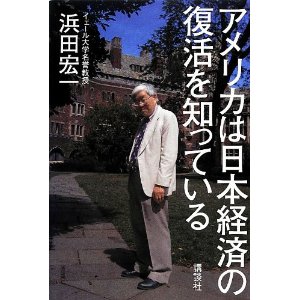
2013年06月18日
2030年世界はこう変わる
若い頃からこの類の本を読むのが好きだった。これからの時代がどう変わるのか、その中で自分はどういう方向に向かうべきなのか常に考えながら生きてきた。18年前、起業したのもそこにしかチャンスがないと自分で予測したからだ。起業して良かったと思っている。2030年といえば今から17年後、僕が生きていれば70歳の年齢である。逆に言えば元気に生きられる(かも知れない)17年間の世界がどのように変わっていくか、興味はつきない。
サブタイトルが”アメリカ情報機関が分析した「17年後の未来」”となっているからかなり高い確率の未来なのかも知れない。この本によると既に日本は成長が終わった国とされている。まぁ人口減少が進むので致し方ないところだろう。日本経済にとってもしかしたら今回のアベノミクスが最後のチャレンジとなるのか、17年後に(生きていれば)歴史を振り返ってみたい。
この本の中で特に興味深かったのは、経済が飛躍的に成長する「機会の窓」が開いていた時期は日本では1965年から1995年であったということだ。1995年は僕が起業した年、バブル崩壊直後である。「機会の窓」が閉じて以降の20年間で日本の国際競争力は大きく変化した。代わって台頭してきた中国の世界における存在感が大きくなっている。著書によると次の成長国は間違いなくインドという事になる。
この17年間で人類は大きな難問に幾度も直面するだろう。気候問題、食糧問題、資源問題、地域紛争、しかしそれらを乗り越えて17年後が平和で豊かな未来であることを期待している。
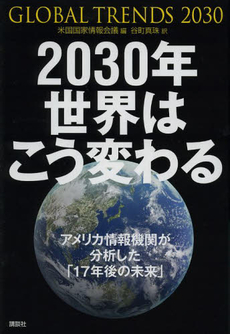
サブタイトルが”アメリカ情報機関が分析した「17年後の未来」”となっているからかなり高い確率の未来なのかも知れない。この本によると既に日本は成長が終わった国とされている。まぁ人口減少が進むので致し方ないところだろう。日本経済にとってもしかしたら今回のアベノミクスが最後のチャレンジとなるのか、17年後に(生きていれば)歴史を振り返ってみたい。
この本の中で特に興味深かったのは、経済が飛躍的に成長する「機会の窓」が開いていた時期は日本では1965年から1995年であったということだ。1995年は僕が起業した年、バブル崩壊直後である。「機会の窓」が閉じて以降の20年間で日本の国際競争力は大きく変化した。代わって台頭してきた中国の世界における存在感が大きくなっている。著書によると次の成長国は間違いなくインドという事になる。
この17年間で人類は大きな難問に幾度も直面するだろう。気候問題、食糧問題、資源問題、地域紛争、しかしそれらを乗り越えて17年後が平和で豊かな未来であることを期待している。
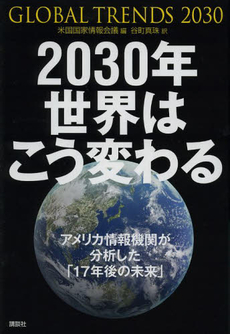
2013年04月03日
永遠の0
百田尚樹さんの本を読むのはこれが初めてである。Facebookで友人から教わった。
こんな素晴らしい本に出合えて幸せである。戦後68年が経とうとしているが、時間の経過とともに忘れ去られてはいけない過去がある。この本は生きる上で何が大切なのかを僕に教えてくれた。それは今の境遇の僕に強烈なメッセージとなった。著者に感謝したい。
僕は昭和35年生まれで戦後15年後に生まれた。日本の高度成長期の中で育ち、仕事を覚え、バブル崩壊後に会社を起業した。とても恵まれたときに仕事ができたと思っている。起業した後、人に言えない苦労があったけれど、この本の中に出てくるような特攻隊員が受けた苦しみや悲しみとは比べようがないほど小さなものだ。
この本で僕の過去の戦争に対する歴史観も大きく変わった。この本の中に描かれていることが真実だとすれば今、日本国内で起きている諸問題の根本的なものが何かを理解することはそう難しくはない。
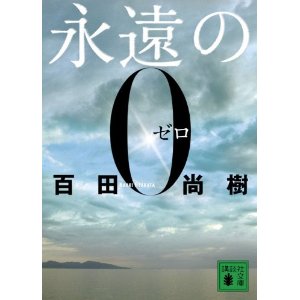
こんな素晴らしい本に出合えて幸せである。戦後68年が経とうとしているが、時間の経過とともに忘れ去られてはいけない過去がある。この本は生きる上で何が大切なのかを僕に教えてくれた。それは今の境遇の僕に強烈なメッセージとなった。著者に感謝したい。
僕は昭和35年生まれで戦後15年後に生まれた。日本の高度成長期の中で育ち、仕事を覚え、バブル崩壊後に会社を起業した。とても恵まれたときに仕事ができたと思っている。起業した後、人に言えない苦労があったけれど、この本の中に出てくるような特攻隊員が受けた苦しみや悲しみとは比べようがないほど小さなものだ。
この本で僕の過去の戦争に対する歴史観も大きく変わった。この本の中に描かれていることが真実だとすれば今、日本国内で起きている諸問題の根本的なものが何かを理解することはそう難しくはない。
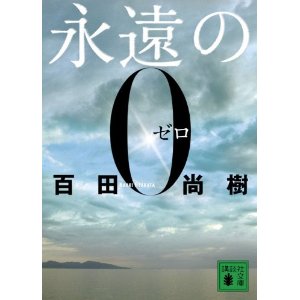
2013年03月13日
シェールガス革命で世界は激変する
長年、お世話になっている産業タイムス社の泉谷社長からサイン入りの本をいただいた。

泉谷さんありがとうございます。しかもなんと僕の尊敬する長谷川慶太郎さんとの共著ではないか!当然、一気に読ませていただいた。
この本はたくさんの人に読んでほしい、そう思った。まさに未来への希望であふれている。既に米国ではシェールガスの産業界での利用が始まっているが、近い将来、必ず日本での利用が始まるだろう。そうなれば日本のエネルギー事情もがらりと変わってくる。なんといっても1キロワットあたり6円という低コストで発電できるのだから。ちなみに石油を使った火力発電で10円、太陽光発電の現在の買い取り価格の42円(来年度は少し下がるらしいが)と比較して話にならない低コストなのである。
更にシェールガスは二酸化炭素の発生量も低く環境にも優しい。いいことづくめだ。僕は自然エネルギーを否定するするつもりはないけれど効率が悪すぎる。現在、全国のあちらこちらでメガソーラーが建設されているがそのブームも早晩終わるかも知れない。260箇所のメガソーラーの候補地があるらしいが、そこで賄える電力は僅か39万世帯分、これでは話にならない。日本全体4400万世帯の中の1%にも満たない。
シェールガスが普及すれば世の中がらりと変わる。既に米国の製造業は中国から引き揚げて本国回帰が始まっているようだ。日本もそうなることを期待したい。また中東などの産油国の情勢も大きく変化するだろうし、原子力発電も将来不要になる可能性が高い。シェールガスを使った火力発電で十分カバーできる。今後、株式市場でもシェールガス関係銘柄が注目されるに違いない。
まさにシェールガス革命だ。その革命を支えている技術には日本のガスタービンをはじめ数多くの技術が使われている。素晴らしい。石油社会からガス社会への転換、パラダイムシフトだ。


泉谷さんありがとうございます。しかもなんと僕の尊敬する長谷川慶太郎さんとの共著ではないか!当然、一気に読ませていただいた。
この本はたくさんの人に読んでほしい、そう思った。まさに未来への希望であふれている。既に米国ではシェールガスの産業界での利用が始まっているが、近い将来、必ず日本での利用が始まるだろう。そうなれば日本のエネルギー事情もがらりと変わってくる。なんといっても1キロワットあたり6円という低コストで発電できるのだから。ちなみに石油を使った火力発電で10円、太陽光発電の現在の買い取り価格の42円(来年度は少し下がるらしいが)と比較して話にならない低コストなのである。
更にシェールガスは二酸化炭素の発生量も低く環境にも優しい。いいことづくめだ。僕は自然エネルギーを否定するするつもりはないけれど効率が悪すぎる。現在、全国のあちらこちらでメガソーラーが建設されているがそのブームも早晩終わるかも知れない。260箇所のメガソーラーの候補地があるらしいが、そこで賄える電力は僅か39万世帯分、これでは話にならない。日本全体4400万世帯の中の1%にも満たない。
シェールガスが普及すれば世の中がらりと変わる。既に米国の製造業は中国から引き揚げて本国回帰が始まっているようだ。日本もそうなることを期待したい。また中東などの産油国の情勢も大きく変化するだろうし、原子力発電も将来不要になる可能性が高い。シェールガスを使った火力発電で十分カバーできる。今後、株式市場でもシェールガス関係銘柄が注目されるに違いない。
まさにシェールガス革命だ。その革命を支えている技術には日本のガスタービンをはじめ数多くの技術が使われている。素晴らしい。石油社会からガス社会への転換、パラダイムシフトだ。

2012年10月31日
このムダな努力をやめなさい
日本マイクロソフト元社長の成毛眞さんの著書である。色んな考え方があると思うけど、こういう考え方もあるんだな、というかかなり的を得ているのではないだろうかと思った。サブタイトルの「偽善者になるな、偽悪者になれ」というのも面白い。
”自分が「やりたいこと」「好きなこと」「得意なこと」で思う存分本領を発揮する。それが成功への最短距離である。だからムダな努力をしているヒマなどはない”(本文より)
2時間ほどで一気に読んだけど楽しく読ませていただいた。

”自分が「やりたいこと」「好きなこと」「得意なこと」で思う存分本領を発揮する。それが成功への最短距離である。だからムダな努力をしているヒマなどはない”(本文より)
2時間ほどで一気に読んだけど楽しく読ませていただいた。

2012年06月20日
采配(さいはい)
今週の月曜日6月18日、落合博満氏の講演を聞く機会があった。僕はプロ野球はほとんど見ないのだがロッテ選手時代から大打者であることくらいは知っていた。また監督になってからも素晴らしい実績を残してきた方だし、どういうお話をされるのか興味はあったが、結論だけ申し上げるととてもためになる講演だった。
それは元プロ野球選手というよりも、人生を成功させた人の話として引きつけられた。一流、超一流という人は違うなと改めて認識した次第である。講演後、落合氏の著書が販売されていたので早速購入した。聞くところによると35万部も売れているらしい。
「采配」という名の著書であるがこれが大変ためになる。自社の幹部には是非読ませようと思っている。またこれは野球人だけでなく、あらゆるスポーツのプロを目指す人や、会社経営者、中間管理職の方も読んでためになるし、新入社員の教育本にも使えるだろう。正直この本を読んで僕は落合氏のファンになった。
「仕事で目立つ成果を上げようとすることと、人生を幸せに生きて行こうとすることは、全く別物と考えているのである」(著書より)
「一度きりの人生に悔いのない采配を振るべきではないか」(著書より)
落合氏の講演を聞けたことに感謝している。そしてこの本に出会って良かったと思う。
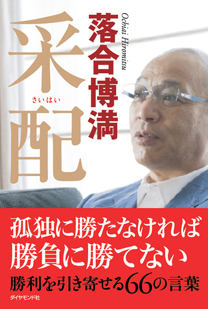
それは元プロ野球選手というよりも、人生を成功させた人の話として引きつけられた。一流、超一流という人は違うなと改めて認識した次第である。講演後、落合氏の著書が販売されていたので早速購入した。聞くところによると35万部も売れているらしい。
「采配」という名の著書であるがこれが大変ためになる。自社の幹部には是非読ませようと思っている。またこれは野球人だけでなく、あらゆるスポーツのプロを目指す人や、会社経営者、中間管理職の方も読んでためになるし、新入社員の教育本にも使えるだろう。正直この本を読んで僕は落合氏のファンになった。
「仕事で目立つ成果を上げようとすることと、人生を幸せに生きて行こうとすることは、全く別物と考えているのである」(著書より)
「一度きりの人生に悔いのない采配を振るべきではないか」(著書より)
落合氏の講演を聞けたことに感謝している。そしてこの本に出会って良かったと思う。
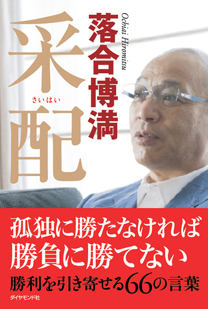
2011年03月27日
スティーブ・ジョブズ 失敗を勝利に変える底力
アップル創業者、スティーブ・ジョブズ氏の生き方はとても参考になります。
成功と挫折、そしてまた成功・・・。
「諦めない勇気の大切さ」 と 「成功と失敗は紙一重」 なのだということが分かる本です。
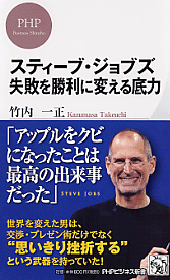
成功と挫折、そしてまた成功・・・。
「諦めない勇気の大切さ」 と 「成功と失敗は紙一重」 なのだということが分かる本です。
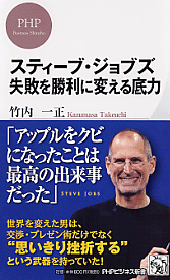
2011年03月27日
孫正義「規格外」の仕事術
ソフトバンク創業者の孫正義さんのことが良く分かる本です。ソフトバンクの元社長室長から見た身近な孫正義さんが語られています。
孫正義さんは三百年後の社会でも歴史の中に登場してくる人物のような気がします。

孫正義さんは三百年後の社会でも歴史の中に登場してくる人物のような気がします。

2010年08月30日
20歳のときに知っておきたかったこと
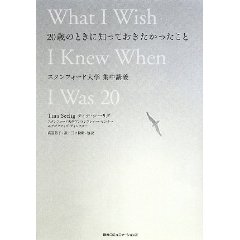
先週の50歳の誕生日を迎える前日にこの本を読んだ。サブタイトルに「スタンフォード大学集中講義」と記載されている、起業家向けの本である。これから起業を考えている人には是非とも手にとって欲しい本であるが、既に起業している人にもおおいに参考となる本であろう。僕もこの本から智慧と勇気をもらった気がする。
What I wish I knew when I was 20.
原文のタイトルである。10年後、今の自分(50歳)を振り返ってあの時にこの事を知っておけば良かった、あの時にああしておけば良かったとならないような悔いのない10年間を過ごしていきたいと思っている。
What I wish I knew when I was 50.
どんな未来が待っているのだろう、わくわくしてきた。
2010年02月07日
最幸の法則
どうしてこうも涙腺が弱いのか、ときどき自分でもあきれる。でもこの本を読んで涙を流さない人は少ないはずだ。この本を読み終えると、前向きな気持ちが、そして優しい気持ちが涙と共に溢れ出てくる。そんな8つの実話をまとめた本である。
第1話「たった二ヶ月だけの妹」からいきなり泣いてしまった。フィクションではない、現実にあった話だから、なおさら心に響く。目標を見失っている人、これから何かをしようと思っている人には是非とも手にとってもらいたい一書である。尚、読むときにはハンカチを手元に置いておくことをお勧めします。
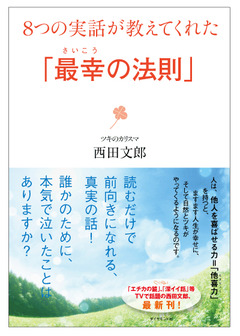
8つの実話が教えてくれた「最幸の法則」
西田文朗 著
ダイヤモンド社 発刊
第1話「たった二ヶ月だけの妹」からいきなり泣いてしまった。フィクションではない、現実にあった話だから、なおさら心に響く。目標を見失っている人、これから何かをしようと思っている人には是非とも手にとってもらいたい一書である。尚、読むときにはハンカチを手元に置いておくことをお勧めします。
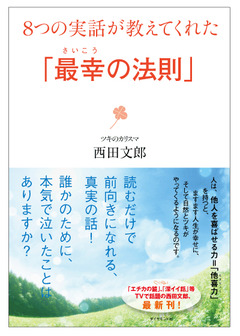
8つの実話が教えてくれた「最幸の法則」
西田文朗 著
ダイヤモンド社 発刊
2010年01月12日
死ぬときに後悔すること25

最近は本を読むペースが異様に速い。さてこの本の著者の大津秀一氏は緩和医療医という肩書きだ。主に末期ガンの人に対する痛みをやわらげる医療を施しているらしい。
1000人の人の死を見届けた終末期医療の専門家が書いた本だけに説得力がある。数多くの終末期医療の経験を通して人が死ぬときに後悔することの代表例を25に集約して紹介している。
この本は書店でふと目について思わず買ってしまった本である。人はいつかは他界する。今生の世との別れ方はひと様々だ。事故で亡くなる方もいるし、病気で亡くなる方もいる。しかし中でもこの末期ガンの方の死との対峙の仕方はまた独特のものがあるような気がする。
余命を宣告された、もしくは自覚した人は今までの人生の何を後悔するのであろうか、その共通点は少なくはないはずだ。元気な人は死が訪れることを自覚することは難しい。それでも確実に訪れる未来の出来事を迎える前に、これからの自分は何をなすべきか、この本を読んで深く考えさせられた。
現在の価値判断の基準を未来の自分に委ねることが出来るとしたら、きっと後悔の少ない人生になるのではないだろうか・・・この本を読んでそう思った。
2010年01月07日
龍馬伝Ⅰ
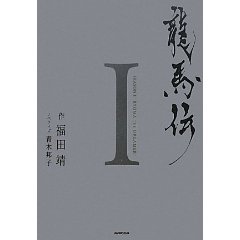
『龍馬伝』・・・今年のNHK大河ドラマである。どうやらこの本はTVの台本を元に小説化したものらしく、表紙にはノベライズと記載されている。それだけに小説のテンポも小気味良く一気に読んでしまった。
坂本龍馬を演ずる主役が福山雅治さんと知ってこれは絶対見ないといけないと思い、どうせなら小説も読んでおこうと思って正月の読書の一冊に加えた次第である。ちなみに僕は福山雅治さんの大ファンなのだ。
歴史上の人物で好きな人はと尋ねられたら、『坂本龍馬』と答える人は少なくないであろう。そういえば若きころ、司馬遼太郎さんの『竜馬がゆく』を読んで、僕にもこの世の中を変える力があるのだろうかと大層なことを考えた事があった。
『龍馬伝』は『竜馬がゆく』とはまた違った趣を感ずる。岩崎弥太郎の見た坂本龍馬という設定からなのかどうか分からないが、『龍馬伝』の龍馬の方が僕には身近に感じてられてならない。
今年は日曜日の夜が待ち遠しい。
2009年10月16日
不毛地帯
昨夜からTV放映が始まった「不毛地帯」は僕の好きな作家・山崎豊子氏原作の著書である。20代のころこの本と出合って大変感銘したのを記憶している。あらすじは覚えているのでこれから毎週放映が楽しみだ。
不撓不屈(ふとうふくつ)、主人公の壱岐正の生きざまを思うにこの言葉が浮かぶ。どんな状況でもあきらめてはいけない、僕はこの本からそのような事を教わった気がする。

不撓不屈(ふとうふくつ)、主人公の壱岐正の生きざまを思うにこの言葉が浮かぶ。どんな状況でもあきらめてはいけない、僕はこの本からそのような事を教わった気がする。

2009年06月11日
パラドックス13
東野圭吾さんの新刊が書店で山積みされていたので手にとった。『パラドックス13』、二日で一気に読んでしまった、面白かった。
SF小説のジャンルになると思うがやはり東野圭吾さんの本だ、期待はずれはない。ちなみにパラドックス (paradox) とは、正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が得られる事らしい。
この本を読み終えてふと考えた。もしも人生がある地点まで戻れるとしたら僕はどの地点まで戻りたいのだろうかと・・・。

SF小説のジャンルになると思うがやはり東野圭吾さんの本だ、期待はずれはない。ちなみにパラドックス (paradox) とは、正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が得られる事らしい。
この本を読み終えてふと考えた。もしも人生がある地点まで戻れるとしたら僕はどの地点まで戻りたいのだろうかと・・・。

2009年02月03日
そうか、もう君はいないのか
一昨年の3月にお亡くなりになった城山三郎氏の遺稿をまとめた本である。城山文学といえば新しいジャンルの経済小説を開拓したことでも有名だ。「総会屋錦城」「男子の本懐」「落日燃ゆ「冬の派閥」」など後世に語り継がれる作品も多い。僕も著者の作品でずい分と世の中の仕組みを勉強させていただいた事に感謝している。
君とは妻・容子さんの事だ。全編に亘り著者の優しさがあふれていてその人柄を偲ばせる。短い本であり1時間程度で一気に読んでしまう。何もない休日の午後に読むことをお勧めしたい。きっと幸福な気持ちに包まれるはずだ。
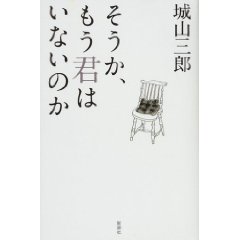
君とは妻・容子さんの事だ。全編に亘り著者の優しさがあふれていてその人柄を偲ばせる。短い本であり1時間程度で一気に読んでしまう。何もない休日の午後に読むことをお勧めしたい。きっと幸福な気持ちに包まれるはずだ。
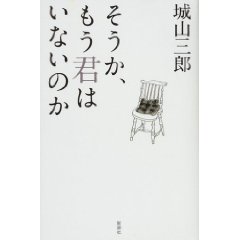
2009年01月14日
さまよう刃
東野圭吾さんの大ファンで最近も3冊ほど読んだ。なかでもこの 「さまよう刃(やいば)」 は一気に読んでしまった。4,5年前に発刊された本なので読まれた方も多いに違いない。いろんなことを考えさせられる本である。
正義とは?未成年犯罪とは?罪のない人が事件に巻き込まれたときにどうなるのか?決して他人事ではない世相を見せている昨今、この本が発しているメッセージは重い。本を手にとられるときは時間のある時をおすすめします。そう読み始めると止まらないからである。

正義とは?未成年犯罪とは?罪のない人が事件に巻き込まれたときにどうなるのか?決して他人事ではない世相を見せている昨今、この本が発しているメッセージは重い。本を手にとられるときは時間のある時をおすすめします。そう読み始めると止まらないからである。

2008年05月09日
マンガ 読むだけで・・・
『マンガ 読むだけでチョットよくなるあなたの英会話』 という本を出版したということで本城式英会話の本城武則さんが来社されました。この本の面白いところは随所にマンガが挿入されていることです。本屋に山積みされているみたいで皆さんにも是非ご一読をお勧めします。

※5月19日までブログ更新を中断します。
※5月19日までブログ更新を中断します。