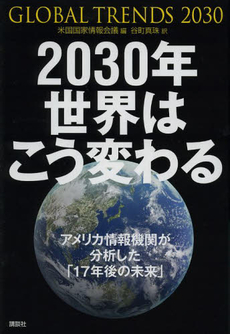2013年06月18日
2030年世界はこう変わる
若い頃からこの類の本を読むのが好きだった。これからの時代がどう変わるのか、その中で自分はどういう方向に向かうべきなのか常に考えながら生きてきた。18年前、起業したのもそこにしかチャンスがないと自分で予測したからだ。起業して良かったと思っている。2030年といえば今から17年後、僕が生きていれば70歳の年齢である。逆に言えば元気に生きられる(かも知れない)17年間の世界がどのように変わっていくか、興味はつきない。
サブタイトルが”アメリカ情報機関が分析した「17年後の未来」”となっているからかなり高い確率の未来なのかも知れない。この本によると既に日本は成長が終わった国とされている。まぁ人口減少が進むので致し方ないところだろう。日本経済にとってもしかしたら今回のアベノミクスが最後のチャレンジとなるのか、17年後に(生きていれば)歴史を振り返ってみたい。
この本の中で特に興味深かったのは、経済が飛躍的に成長する「機会の窓」が開いていた時期は日本では1965年から1995年であったということだ。1995年は僕が起業した年、バブル崩壊直後である。「機会の窓」が閉じて以降の20年間で日本の国際競争力は大きく変化した。代わって台頭してきた中国の世界における存在感が大きくなっている。著書によると次の成長国は間違いなくインドという事になる。
この17年間で人類は大きな難問に幾度も直面するだろう。気候問題、食糧問題、資源問題、地域紛争、しかしそれらを乗り越えて17年後が平和で豊かな未来であることを期待している。
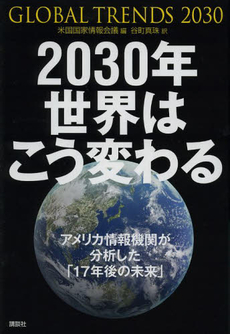
サブタイトルが”アメリカ情報機関が分析した「17年後の未来」”となっているからかなり高い確率の未来なのかも知れない。この本によると既に日本は成長が終わった国とされている。まぁ人口減少が進むので致し方ないところだろう。日本経済にとってもしかしたら今回のアベノミクスが最後のチャレンジとなるのか、17年後に(生きていれば)歴史を振り返ってみたい。
この本の中で特に興味深かったのは、経済が飛躍的に成長する「機会の窓」が開いていた時期は日本では1965年から1995年であったということだ。1995年は僕が起業した年、バブル崩壊直後である。「機会の窓」が閉じて以降の20年間で日本の国際競争力は大きく変化した。代わって台頭してきた中国の世界における存在感が大きくなっている。著書によると次の成長国は間違いなくインドという事になる。
この17年間で人類は大きな難問に幾度も直面するだろう。気候問題、食糧問題、資源問題、地域紛争、しかしそれらを乗り越えて17年後が平和で豊かな未来であることを期待している。